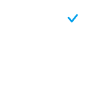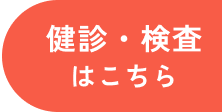診療時間
5Fで診療を行っております。
| 診療 時間 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~ 12:30 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14:30~ 18:00 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
※最終受付(午前・午後)診療時間終了の30分前
休診日…日曜午後
循環器疾患でよくある症状
- 脈が乱れる(脈が飛ぶ)
- 脈が速くなる
- 脈が遅くなる
- 動悸
- 息切れ
- めまい
- 失神
- 肩が異常なほど凝る(張る)
- 胸の圧迫感(胸痛)
- 手足のむくみ
- 手足の痺れ
- 手足の痛み
- 夜中に息苦しさで目が覚める
など
循環器疾患でよくある病気
- 高血圧
- 糖尿病
- 脂質異常症
- 不整脈(心房細動、期外収縮、上質頻拍症など)
- 狭心症(労作性と冠攣縮性)・急性もしくは陳旧性心筋梗塞(虚血性心疾患)
- 心不全(虚血性、弁膜症性、高血圧性、心筋症)
- 肺血栓塞栓症
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 睡眠時無呼吸症候群
など
高血圧
高血圧は、血管内の血液圧が異常に高くなる状態で、心臓病や脳卒中、腎不全などのリスクを高めます。主な原因には、遺伝、肥満、塩分の摂り過ぎ、運動不足、ストレスなどがあります。特に動脈硬化が進むことで、心臓や脳への負担が増し、重大な合併症を引き起こす可能性があります。治療は食事療法、運動、薬物療法があり、定期的な血圧測定が重要です。生活習慣の改善により予防が可能ですが、早期発見と早期治療が求められます。
糖尿病
糖尿病は、血糖値が異常に高くなる病気で、心血管疾患の主要なリスク因子とされています。インスリンの分泌不足や作用の低下により、血糖コントロールが困難になります。糖尿病になると動脈硬化や高血圧、脂質異常症を併発しやすく、心筋梗塞や脳卒中のリスクが増加します。治療には食事療法、運動、薬物療法があり、定期的な血糖値の測定が重要です。
脂質異常症
脂質異常症は、血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪)のバランスが崩れた状態を指します。特にLDLコレステロールの増加やHDLコレステロールの減少は、動脈硬化を促進し、心血管疾患のリスクを高めます。原因には食生活の偏りや運動不足、遺伝的要因があります。治療には食事療法や運動、薬物療法があり、生活習慣の見直しが重要です。定期的な血液検査による脂質のチェックが推奨され、早期の対応が合併症の予防に繋がります。
不整脈
不整脈は、心拍が不規則になる状態で、心房細動や期外収縮、上室性頻拍などが含まれます。心臓の電気信号の異常により、心拍が速くなったり遅くなったりすることがあります。不整脈は脳卒中や心不全のリスクを高めるため、早期の診断と治療が重要です。治療方法は、生活習慣の改善、薬物療法、時にはカテーテルアブレーションなどが行われます。定期的な心電図検査が必要です。
狭心症
狭心症は、心臓の血流不足により胸痛や圧迫感を引き起こす病気です。主に冠動脈の動脈硬化が原因で、運動やストレスによって症状が悪化します。発作が起きると、胸が締め付けられるような痛みが現れ、休息することで軽減します。治療には、生活習慣の改善、薬物療法(血管拡張薬や抗血小板薬)、時には冠動脈バイパス手術やカテーテル治療が必要です。バイパス手術やカテーテル治療が必要な場合、連携する医療機関をご紹介いたします。
心不全
心不全は、心臓が十分な血液を送り出せない状態を指します。原因は高血圧、心筋梗塞、心筋症など多岐にわたり、息切れ、浮腫、疲労感が主な症状です。心不全が進行すると、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。治療は生活習慣の改善、薬物療法(利尿薬やACE阻害薬)、重度の場合は心臓移植や補助人工心臓が考慮されます。心不全の早期診断と管理が重要です。
肺血栓塞栓症
肺血栓塞栓症は、血栓が肺の血管を塞ぐことで発生する病気です。深部静脈血栓症が原因となることが多く、急激な息切れや胸痛、咳血が特徴です。緊急事態であり、迅速な診断と治療が必要です。治療法は抗凝固療法が主で、重症の場合は血栓溶解療法や手術が必要です。長時間の安静(長時間動かないこと)や肥満などがリスク要因となります。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に一時的に呼吸が停止する状態です。いびきや日中の眠気が主な症状で、高血圧や心不全のリスクを高めます。原因は肥満や気道の狭窄などで、診断にはポリソムノグラフィーを使用します。治療法は生活習慣の改善やCPAP療法が中心です。